労働法改正に関するコラム
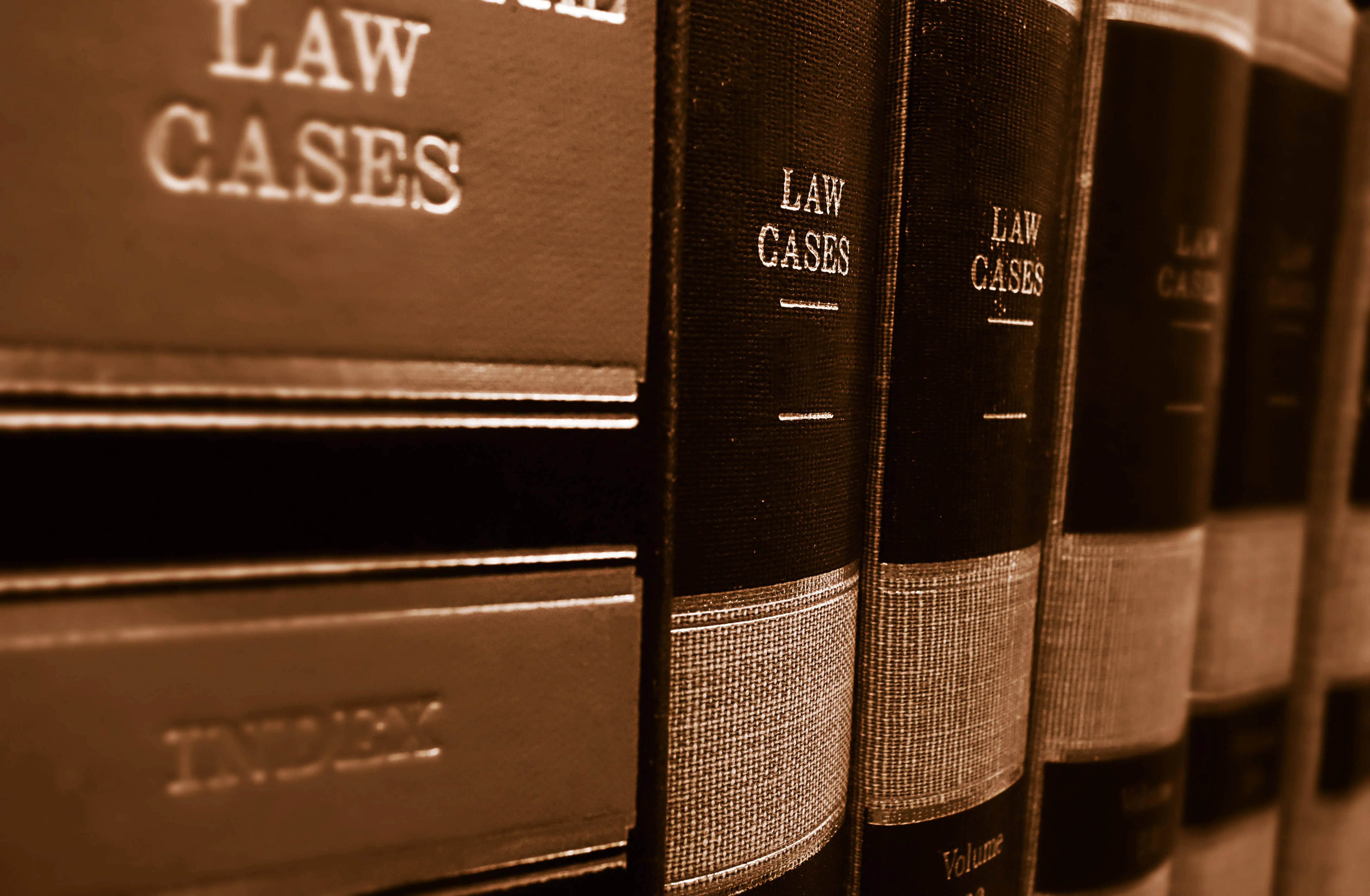
労働法改正に関するコラム
令和4年10月1日より、育児介護休業法の改正に伴い、新たに出生時育児休業(通称:産後パパ育休)がスタートします。この制度は、育児に対する父親の関与を促進し、子育てと仕事の両立を支援することを目的としています。
また、この制度の適用を受け、受給要件を満たした父親は「出生時育児休業給付金」を受け取ることができ、経済的な支援も受けられるようになりました。
今回は、この「産後パパ育休」に関する給付金である「出生時育児休業給付金」の受給要件と具体的な手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
産後パパ育休とは、育児・介護休業法に基づく、育児休業制度の一つで、赤ちゃんが生まれた日から一定期間内(出生後8週週間以内)に父親が取得できる育児休業を指します。
産後パパ育休は、男性が子どもの出生直後に柔軟に育休を取得できるように設けられた制度です。この制度を通じて、男性も女性とともに育児の大変さや喜びを実感し、その後の育児への関わり方や仕事とのバランスを考えるきっかけになることが期待されています。
産後パパ育休についての詳細は、下記のコラムにて詳細を記載しておりますので、ご確認ください。
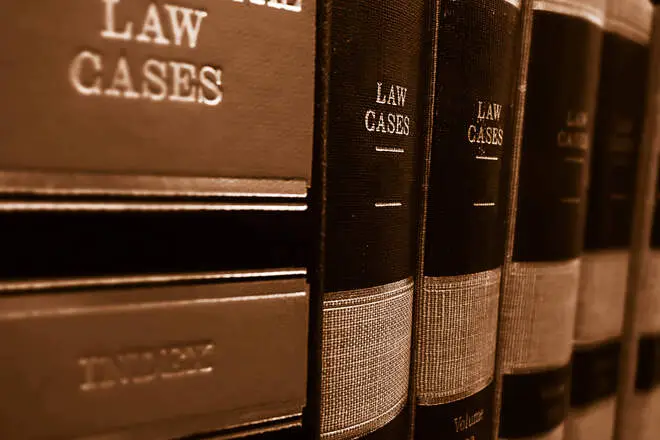
出生時育児休業(産後パパ育休)給付金を受給するには、次の①~④の要件すべてに当てはまる必要があります。
子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休を取得した被保険者であること |
産後パパ育休を取得できるのは、赤ちゃんが生まれた日(出生日)から8週間以内です。
父親はその期間内であれば、最大4週間(28日間)まで産後パパ育休を取ることができます。例えば、赤ちゃんが生まれた日から8週間の間で、好きなタイミングで4週間以内の期間を選んで育休を取ることができる、ということです。
ちなみに、余談ですが、「8週間を経過する日の翌日」とは非常にわかりにくいですが、「産後の終了日」と読み替えていただければと思います。
このような複雑な表現になっているのは
・産後休業の開始は、出生日の翌日からであること
・産後パパ育休の取得可能期間の開始は、出生日であること
この1日の誤差があるため、このような表現になっているのではないかと考えます。
以下に具体的なスケジュール例を記載します。
出生日 | 8月1日に生まれた子 |
| 産後休業期間 | 8月2日〜9月26日 |
| 産後パパ育休(取得可能期間) | 8月1日〜9月26日 |
この4週間(28日)以内というのは、2回に分割して取得することも可能なので、産後すぐに2週間取得して、2回目は少しあけてまた2週間取得するということもできます。
ただし、分割する場合は2週間前までに事前に申請しておくことが必要なので、留意が必要です。
なお、産後パパ育休を取得する場合は、出産予定日または出生日のいずれか早い日から出生時育児休業給付金の対象となります。
休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること |
まず、この給付金を受給する労働者は、常の育児休業給付金と同様に雇用保険被保険者である必要があります。
受給資格についても育児休業給付金と同じく、賃金支払基礎日数の要件があります。
産後パパ育休中の就業日数が最大10日以下であること(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下であること) |
「なんで産後パパ育休中に就業日数の話が出てくるの?」と疑問に感じる人もいると思いますが、「産後パパ育休中であっても出勤が必要になることもあるでしょう」という理解でよいと思います。
ここでいう「最大10日以下」又は「最大80時間以下」というのは、産後パパ育休を最大28日間(4週間)取得した場合の制限です。産後パパ育休が28日間(4週間)より短い場合は、その日数に比例按分して就業可能日数(時間)を計算することになります。
ここは非常にわかりにくいので、下表に例示します。
例えば・・・産後パパ育休14日間の場合 |
|---|
比例按分により、最大5日(5日を超える場合は40時間)が就業可能日数ということになります。 日数 10日×14日/28日=5日 時間 80h×14日/28日=40h |
上記はちょうど半分の例ですが、割り切れない場合は以下の通りです。
例えば・・・産後パパ育休10日間の場合 |
|---|
比例按分により、最大4日(4日を超える場合は約28.57時間)が就業可能ということになります。 日数 10日×10日/28日≒0.357日→4日(端数切り上げ) 時間 80h×10日/28日≒28.57h(端数処理無し) |
さて、この要件、なぜ日数と時間が出てくるのでしょうか?
これは産後パパ育休における「就業」の考え方に「1日就業」だけではなく「部分就業」という考え方があるからです。簡単にいえば「半休」のように出勤したりすることが想定されています。
このため、10日を超えたとしても、80時間以下であれば、この要件を満たすことになります。
例えば産後パパ育休を10日取得した場合、上表の例では就業可能日数は最大4日間ということになります。ただし、仮に、6日働いたとしても、他の2日間が部分就業であり、就業合計が28.57h以下におさまるなら、要件を満たすということになります。
「子の出生日から8週間を経過する日の翌日」から「6か月を経過する日」までに、「その労働契約の期間」が満了することが明らかでないこと |
「子の出生日から8週間を経過する日の翌日」とは予定通り産まれた場合は「産後終了日」のことです。
「その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと」とは、「有期契約を更新しない」ことが決まっている場合を除き、すべて適用という理解になります。
例えば、産後終了日から半年後には期間満了により退職することが確定している人は、受給要件から外れることになります。
多くの有期雇用契約書にみられる「更新する可能性あり」という文言がある場合は「不更新が明らかになっていない」ため、この受給要件については満たしていることになります。
支給要件が複雑な産後パパ育休ですが、給付金は育児休業と同じ計算方法です。
休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数(28日上限)×67% |
出生時育児休業(産後パパ育休)給付金が支給された日数は、育児休業給付金の支給率67%の上限日数である180日に通算されます。
また、産後パパ育休期間中の就労に対して事業主から賃金が支払われた場合は、賃金額に応じて支給額が調整されます。ここでいう賃金とは、産後パパ育休期間を含む賃金月分として支払われた賃金のうち、次の額をいいます。
産後パパ育休給付金に関する就労賃金の取り扱いについては、通常の育児休業給付金とは異なりますのでご注意ください。
出生時育児休業期間に就労等した日数・時間に応じて支払われた額 |
|---|
就労した場合の賃金のほか、出生時育児休業期間に応じて支払われる手当等を含みます。 なお、通勤手当、家族手当、資格等に応じた手当等が、就労等した日数・時間にかかわらず一定額が支払われている場合は含みません。 |
月給制の場合は、以下の通り日割します。
就業規則等で月給制等となっており、出生時育児休業期間を対象とした日数・時間が特定できない場合は、日割計算をして得られた額(小数点以下切り捨て) |
|---|
「支払われた賃金額」 × 『「出生時育児休業取得日数」 ÷ 「出生時育児休業期間を含む賃金月の賃金支払対象期間の日数」』 |
| (具体的な計算例) 支払われた賃金額=300,000円 出生時育児休業取得日数=15日 賃金支払基礎日数=30日 →300,000×(15÷30)=150,000円 |
出生時育児休業(産後パパ育休)給付金の支給を受けるには、産後パパ育休を開始した被保険者を雇用している事業主の方が、以下の受給資格確認・支給申請の手続を行う必要があります。
このため、従業員からの問い合わせ時に、混乱しないよう労務担当者は、厚生労働省のパンフレットをよく読んで様式の記載方法も理解しておきましょう。(本コラムの文末に参考リンクを貼っておきます。)
産後パパ育休給付金の申請手続きは、通常の育児休業給付金の申請書とは別に、「出生時育児休業給付金支給申請書」を用いて行います。
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日(産後終了日)から申請可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日までにハローワークへ申請する必要があります。
なお、産後パパ育休は同一の子について、2回まで分割して取得できますが、申請は1回にまとめて行う必要があります。
通常の育児休業給付金は、支給単位期間の翌日から申請を行うことができますが、出生時育児休業(産後パパ育休)給付金は、取得可能期間を過ぎてからしか申請を行うことができませんので注意が必要です。
後で申請できない、ということにならないよう労使双方で計画的に準備をするようにしておきましょう。
出生時育児休業(産後パパ育休)給付金の申請にあたっての添付書類は以下の通りです。
まずは産後パパ育休を取得していることが客観的に証明できるものとして以下のものが必要です。
①産後パパ育休を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの |
|---|
|
あわせて、出産予定日、出産日を確認するものとして以下のものがあります。
②出産予定日及び出産日を確認することができるもの |
|---|
|
その他、本コラムの「出生時育児休業(産後パパ育休)給付金の支給額は?」でご説明した通り、「産後パパ育休期間を対象として支払われた賃金」を記載する欄もあります。
出生時育児休業給付金の申請は、書面にてハローワークに提出することもできますが、e-Govを利用して電子にて申請することも可能です。
令和4年10月1日より、新規手続きとして「雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請(令和4年10月以降手続き)」がe-Govの申請様式に追加されております。
産後パパ育休は労使ともに計画的に取得することがポイントとなります。スムーズな手続きができるように、事前に対応フローをよく検討しておきましょう。
産後パパ育休が創設されたことで、子どもが生まれた後に父親が育児のために休暇を取りやすくなることが期待されています。
産後パパ育休を取得することで、父親も育児に積極的に参加できる機会が提供されます。正確な情報をもとに、計画的に育児休業を取得し、家族全員にとって充実した時間を過ごせるよう、この制度をよりよく活用できるようにしていきましょう。
| 【更新情報】 本記事は最新情報を元にリライトしております。(更新日 令和6年8月30日) |
厚生労働省では、出生時育児休業給付金及び育児休業給付金の手続きについてパンフレットを公表しております。詳しくは下記ページをご参照ください。

この記事を書いた人
平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。IPO(上場)審査に向けた労務デューデリジェンス (労務DD)を数多く実施、給与計算や社会保険実務にも精通した社労士として活躍中。